大避神社(兵庫県赤穂市)
 祭神 天照皇大神 春日大神 秦河勝
祭神 天照皇大神 春日大神 秦河勝独り言神社の山門の手前、左の道を進むと途中に妙見寺観音堂があり山頂は茶臼山です。正面は坂越湾で天然記念物の樹林がある生島が眼下に、右手には千種川を手前に赤穂の市街地が見晴らせます。山頂にテレビ中継用のアンテナ施設があり道は舗装され、歩きやすいのでお勧めです。所要時間は片道40分程度です。
瀬戸内海3大船祭り・天然記念物の生島樹林
生島は立ち入り厳禁
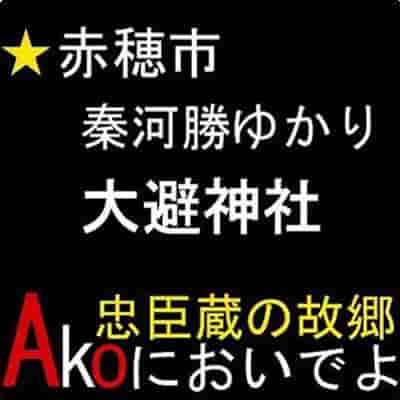
大避神社由緒
拝殿
瀬戸内海三大船祭り
船渡御
御旅所は仏教様式の建物で再建され、神仏習合の名残をみることができますが生島への立ち入は禁止されていています。
生島(いきしま)
生島御旅所と樹林
樹林は国指定天然記念物
周囲1.63kmの小島であるが、古来大避神社の神地として、樹木の伐採が禁止され、原始の状態が保たれ樹種は大部分が常緑樹である。古墳
墳形は直径20mの円墳と考えられ、大避神社の祭神である秦河勝の墳墓と言い伝えられている。御旅所・船倉
御旅所は享保四年十二月に再建されたもので、瓦葺の仏教様式の建物。祭礼では内陣に神輿が安置されて神事がとり行なわれる。船倉は元文元年の建築で、祭礼用和船を保管している。船倉と和船は昭和になり県指定有形文化財になっている。(出典:赤穂市教育委員会)大避神社関連情報
近くの観光スポット
旧坂越浦会所 坂越まち並み館 赤穂海の駅 奧藤酒造郷土館 坂越海岸アクセス

レンタサイクル
JR赤穂・有年・坂越各駅に有り| 住所 赤穂市坂越1299 地図で確認 mapcode 114 037 695 | 坂越駐車場  mapcode 114 037 484 |
秦河勝ゆかりの大避神社へようこそ! (C) 2011 tadeho48
