おせど 大石内蔵助仮寓の地(赤穂市)

浪人した大石内蔵助と家族が仮住まい
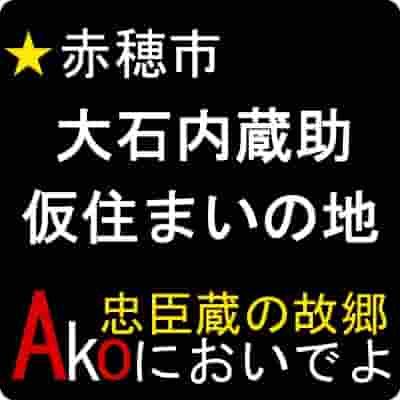
赤穂ではこの地を「おせど」と呼ぶ
赤穂八幡宮の東すぐにあり、大石内蔵助が赤穂城開城の残務整理をする元禄十四年五月七日から山科へ移る六月二十五日までの間、家族と共に仮住まいした所です。この地は平成9年(1997)に赤穂市指定文化財に指定されました。おせどと大石内蔵助

開城の準備と残務整理のため
ここから執務所の遠林寺に通いました。忠僕八助との別れの逸話もこの地でのことと伝わります。遠林寺住職浅野家再興に奔走
浅野家の祈願所として米三十五石が給付されており、大石内蔵助は住職の裕海を江戸に派遣して真言宗の僧のツテから綱吉の母、桂昌院の力を借りて浅野家再興を画策しましたが失敗。遠林寺は随鴎寺の西隣りにありましたがその後、廃寺になっています。伝大石内蔵助仮寓地跡

見所

また「牛石(画像)」「馬石」と呼ばれる巨石があり、もと赤穂城本丸の庭園にあったもので、この石は薩摩の島津家から浅野家に贈られたものといわれています。
独り言古地図をみると「おせど」のあった「宮山」を出て熊見川支流の橋を渡り中州の「中村」を横ぎって再度、熊見川本流の橋を渡り執務所のあった「遠林寺」に残務整理のために通っている。その距離約2キロあまりか。主君を、城を、家臣など全てを失い通った2か月間の心中はいかばかりか、察するにあまりある。
| 住所 赤穂市尾崎738-3 地図で確認 mapcode 541 588 203 | 地図位置情報  赤穂八幡宮 |
おせどのページへようこそ! (C) 2011 tadeho48
