赤穂八幡宮(兵庫県赤穂市)

浅野家および赤穂郡十五か村の氏神
赤穂八幡宮由緒
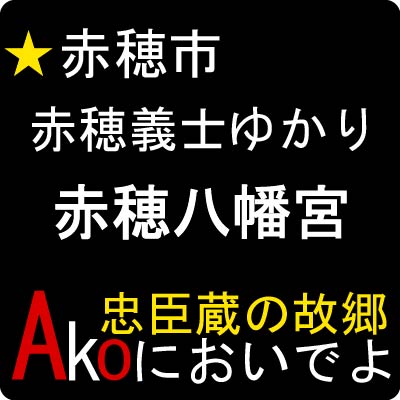
祭神 仲哀天皇 応神天皇 神功皇后
赤穂浅野藩との縁と社宝
大石内蔵助お手植えの櫨の木があり、義士ゆかりの如来寺や重文千手観音菩薩像の普門寺、大石内蔵助が仮住まいした「おせど」があります。浅野長直が赤穂入国の際、近藤三郎左衛門正純(家老で赤穂城の設計をした人)を神宮寺別当宗円に命じた文書、大石良雄自筆の絵馬、貞享四年(1687)に寄進の石灯籠と馬鞍、岡島八十右衛門、原惣右衛門の書等があります。秋祭りの獅子舞
無形民俗文化財
10月に行われる秋祭りの獅子舞の始まりは寛文元年(1661)の赤穂城築造を祝って始まったとされ、「神幸式」の行列で先駆けを務めます。太鼓の打ち出しで目覚めた雌雄の獅子が境内及びお旅所までの道中を鼻高に導かれて御輿の前を清めながら荒々しく舞う勇壮な伝統芸能で平成5年に市文化財、平成17年に兵庫県指定無形民俗文化財に指定されました。茅の輪くぐり 大祓(おおはらい)
大祓は年二回、六月三十日を「夏越の祓い」と呼び、人形の白紙に託して、半年間の穢れを祓い、無病息災を願って茅の葉を束ねた「茅の輪」を「水無月の夏越しの祓いする人は千歳の命のぶというなり」と唱えながら三回くぐります。十二月三十一日を「年越の祓い」と呼び、新年を迎えるために心身を清める祓いです。独り言境内右手の奥に「信仰の道」の石碑があります。この辺りは静寂に包まれ、石畳の坂道をあがると如来寺・普門寺・赤穂塩ゆかりの塩釜神社・太地堂などが並び厳粛な雰囲気が漂います。まさに「信仰の道」、短い距離なのでお参りがてらの散策がお勧めです。
| 住所 赤穂市尾崎203 地図で確認 mapcode 541 588 260使い方 | 電話 0791-42-2068 料金 参詣無料 公式 赤穂八幡宮 |
赤穂八幡宮へようこそ! (C) 2011 tadeho48




