赤穂四十七士泉岳寺へ(赤穂事件)
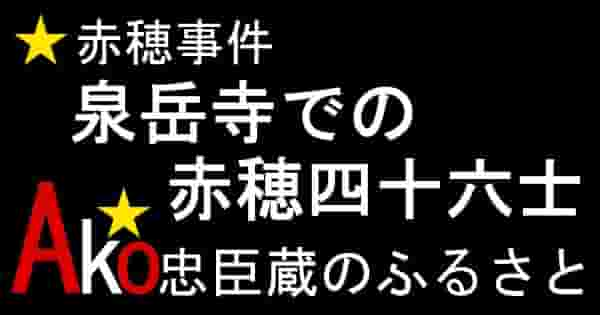
事件は5部構成
刃傷事件赤穂開城 円山会議吉良探索 急襲泉岳寺切腹と遺子その4泉岳寺:回向院で開門を断られた四十七士は予て決めていた道順で泉岳寺を目指します。浪士の泉岳寺での振る舞いや追撃をしなかった上杉家の事情、幕府への自訴と永久の別れなど。
ページ内ジャンプ
泉岳寺へ引揚寺坂吉右衛門失踪泉岳寺での浪士
独り言 西暦(太陽暦)ではいつだったのか? 討ち入りは「元禄十四年十二月十四日」で赤穂義士祭など全ての行事が現在でも12月14日に行われる。が、現在の暦に置き換えると1月30日の火曜日だった。襲撃時刻は午前4時頃なので厳密には1月31日の水曜日。凍てついた道と月光で灯りが不要だったのも肯けます。
引き揚げ前の点呼と負傷者
寺坂吉右衛門は居た!
長安雅山筆「義士引き揚げ」 赤穂市立歴史博物館蔵
赤穂市立歴史博物館蔵
死者はなく負傷者四人
原惣右衛門(塀を乗り越える時の捻挫)神崎与五郎(塀を乗り越える時の捻挫)
横川勘平(刀傷)
近松勘六(泉水に落ち打撲と刀傷)、勘六は左の腹に大きな傷を受け、どうせ長くない命だからと断るのを医者を呼び治療させたと「白明話録」にある。
敵襲を警戒!山鹿流隊列で引き揚げる
一番手 三村包常 神崎則休 茅野常成 二番手 潮田高教 三番手 間光興 村松秀直 岡島常樹 奥田行高 四番手 大石良金 五番手 武林隆重 吉田兼定 六番手 倉橋武幸 勝田武堯 杉野次房 間光風 七番手 横川宗利 近松行重 八番手 吉田兼亮 堀部金丸 早水満堯 間光延 九番手 小野寺秀富 堀部武庸 菅谷政利 中村正辰 中央に大石内蔵助良雄 その後に十八名が三から四人づつ並び 最後に岡野包秀 貝賀友信 千馬光忠 精鋭三人が敵襲に即応できる隊列で引き揚げた。
一路泉岳寺へ
泉岳寺への引き揚げルート
出発・到着・距離
午前六時頃で到着は九時頃、距離は約10km。緻密な計画に驚く
当時の隅田川には両国橋、新大橋、永代橋の橋があり泉岳寺へはいずれかの橋を渡らなければならなかった。両国橋が近道だが毎月朔日、十五日は御禮日で江戸在府の大名、旗本は総登城するのが慣例であり遠回りの永代橋を渡り泉岳寺に向かう。
道順
回向院前 → 一ツ目河岸 → 深川 → 御船蔵通り → 永代橋 → 霊岸島 → 稲荷橋 → 鉄砲州 → 木挽町 → 汐留橋 → 金杉橋 → 芝口 → 高輪泉岳寺。寺坂吉右衛門が消えた!
原惣右衛門の「討入実況報告書」によると、回向院(無縁寺)に向かい開門を頼んだが入れずに少し休んで出発。上杉家や吉良家からの追い討ちを警戒しながら泉岳寺へ到着したときの点呼では四十四人だった。
大目付への自訴で隊列を離れた吉田忠左衛門、富森助右衛門の他に寺坂吉右衛門の姿がなかった。
幕府への自訴と幕府の対応
- 吉田忠左衛門と富森助右衛門が泉岳寺への途中で大目付仙石伯耆守に討ち入りを自訴
- 幕府は幕府目付阿部式部と杉田五郎右衛門を吉良邸へ派遣して吉良上野介の死体検分、吉良義周からの「口上書」提出に基づき実況検分を行った
- 吉良家目付の糟谷平馬は月番老中稲葉丹後守の屋敷へ顛末を届け出た
- 泉岳寺住職の酬山和尚は寺社奉行の阿部飛騨守に届け出る
- 町奉行の松平伊豆守は吉良家の様子を聞く
- 大目付の仙石伯耆守は細川家お預けの十七人から事情聴取を行う
上杉弾正の決断 追撃を中止!
吉良邸が襲撃された時、病臥中の上杉弾正大弼(だいひつ)綱憲は病床から起きあがり、急いで浪士一行を追撃し、一人も討ち洩らしてはならんと命令した。上杉や吉良と親戚になる高家の畠山下総守義寧(よしやす)が駆けつけ、御府内での騒動を引き起こしては相成らんと老中の意向を伝えた為、綱憲は実父上野介への孝道を捨て出撃を中止する。
千坂兵部なる名家老が綱憲を諫めて出撃を断念させた有名な話は兵部が元禄十三年に死亡しており後の創作、当時の家老は色部又四郎でした。
出兵を中止したことへの落首
[影虎の牙折れ爪も抜けはてて永き恥辱の種を上杉]泉岳寺での四十七士
修行僧の白明「白明話録」は貴重な史料
泉岳寺の住職は酬山長恩で曹洞宗の格式の高いお寺で全国から修行僧も多く来ていた。「白明話録」によると「自分は十九歳で泉岳寺にいた。十二月十五日は朝食も終わり、仏さまにお茶を献ずる礼茶の儀式の準備のため、一同は衆寮から出て本堂に集まっていた。そこへ門番がやって来て寺務を掌る副司に、只今もとの浅野内匠頭の家来が五十人余り異様な姿で鑓や長刀を持って門に入ってきたが通しても良いかどうかを尋ねた。副司はびっくりして長恩和尚に相談した結果、役僧頭をやって検分した上でと門へ遣わした所、一行は既に浅野内匠頭の墓のある墓地へ通ったあとであった」とある。註:白明(後の月海和尚)は土佐国の人で後に東福寺の六世住職になった人。
焼香順
吉良上野介の首を洗って亡君冷光院殿の墓前へ供え無念を晴らしたことを報告し焼香に移る。「白明話録」第一は一番鑓の間十次郎
第二は一番刀の武林唯七
第三は大石内蔵助と順次四十一人が焼香
敵襲を警戒しながら休息
大石親子や長老組は客殿に若い人は衆寮(雲水の宿泊所)で休むようにしたが大方の浪士は衆寮の方に集まった。よほどお腹が空いていたとみえて粥を沢山食べその後、お茶、お茶受けを出し風呂を勧めたが敵襲を警戒して誰も入らず、そのうち皆よく眠ってしまわれた。「白明話録」吉良上野介の首請取書が現存
墓前に供えたのち、庫裡から重箱の外箱を取り寄せ納めて終日、衆寮に置いてあったが十六日の晩使僧二名が吉良邸へ届けたとある。「白明話録」吉良家の左右田孫兵衛、斉藤宮内の両家老が書いた受取書が現存する。吉良家の菩提寺万昌院の和尚から仙石伯耆守へ働きかけ幕府の役人の指図のように見せかけて吉良上野介の首を貰い受けた模様が書かれている。「米沢塩井家覚書」
首請取りの落首 [吉良ふなよ首納豆の歳暮かな]
永久の別れ 大目付仙石邸へ出頭命令
老中筆頭の阿部豊後守が将軍綱吉に報告、将軍綱吉は即決の処分を避け、四大名家に分散して収監する事を決め、歩行目付の石川弥一右衛門ら三人が泉岳寺へ出向き「仰せ渡さるる儀があるから即刻仙石伯耆守邸へ参るよう」と申し渡す。午後七時半頃に老人と負傷者は駕籠に乗せ他は歩いて出発。高輪→三田→西久保→愛宕下仙石伯耆守邸へ午後九時頃に到着している。
元禄赤穂事件関連ページ
事件の年譜刃傷事件~赤穂開城 山科隠棲 吉良探索~討ち入り 泉岳寺~切腹~遺族事件の詳細刃傷事件~藩主切腹 浅野家断絶 吉良邸討入り 引き揚げ~泉岳寺 切腹~遺子の処罰
赤穂城・浅野家・吉良家赤穂城古写真など 浅野内匠頭長矩 吉良上野介・左兵衛
吉良邸引き揚げから泉岳寺の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48

