菅谷半之丞政利(赤穂義士)
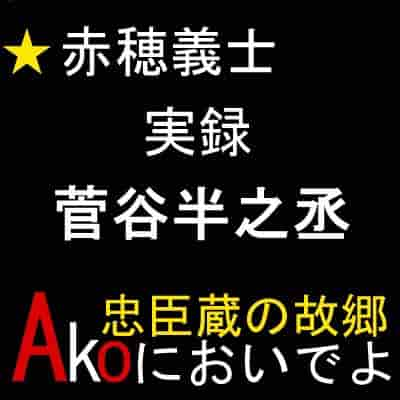

すがやはんのじょう まさとし
刃傷事件勃発当時の役職は馬廻を務める譜代の臣であり当初から義盟に加わる。大石内蔵助と江戸に下り、町人政右衛門と変名して同志と苦労を共にし恩顧に報いた義士。家族・家系図・家紋
菅谷家系図
重ね扉
- 菅谷平兵衛(浅野内匠頭家来)
- 津田五郎左衛門の娘
- 岡本松之助(浪人で備後三次之町在住)
- 八田弥助の妻(浪人)
浅野家譜代の家系
浅野長重が元和元年五月七日、大坂の役で毛利勝長と戦ったとき、名誉の戦死を遂げた二十余人の家来の中に菅谷加兵衛なる名がありこれが半之丞の先祖。性格と容貌
討ち入り姿
- 円山会議後は大石内蔵助の信頼が厚く江戸下りに同行し補佐役で活躍した。
- 浪士中では一番容貌魁偉といわれた人で、美男説の出所は不明で事実とはだいぶ異なるようだ。
開城後居所を転々とする
元禄十五年正月十日赤穂から京都滞在中の早水藤左衛門宛の書状中には「霜月二十一日云々」の記述があるから十一月頃には赤穂に帰っていたと思われる。元禄十五年七月頃までは赤穂に居を構えていたらしいが、七月二十四日付の早水藤左衛門宛の書状に「拙者事も当廿二、三日には爰元(ここもと)立申、足守へ立寄、三次へ帰り申事にて御座候」とあり、七月二十二、三日頃赤穂を発ち郷里の備後三次へ一時帰った。
[江赤見聞記]では伏見にいたことになっているから江戸に下着するまでは赤穂、三次、伏見などで時期の到来を待っていたことになる。
屋敷跡の説明板
半之丞は、浅野家譜代の家柄である。大兵学者山鹿素行が赤穂へ配流されてきた時、まだ七歳の少年であったが、素行配流中はその教えを受けた。後に免許皆伝の大石頼母助良重について山鹿流奥義免許を受けたと伝わる。凶変が起こるや義盟に加わり、江戸に下着するまでは、赤穂、備後三次、伏見などで時機がくるのを待っていた。沈着で物静かな人柄であったため、表立った活躍はしなかったが、東下りには大石内蔵助に従って同行した。
江戸に下着後は、石町三丁目で町人政右衛門と変名し、大石内蔵助の側近にあって作戦参謀の役を務めた陰の功の人であった。
元禄十五年の討ち入りの際は、裏門隊の一員として屋内で奮戦した。
松山藩松平隠岐守の中屋敷にお預けの後、翌年加藤斧右衛門の介錯で切腹した。 赤穂義士会(転載)
生年
| 家系
|
菅谷政利の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48


