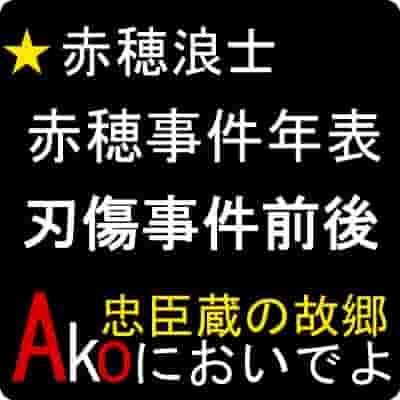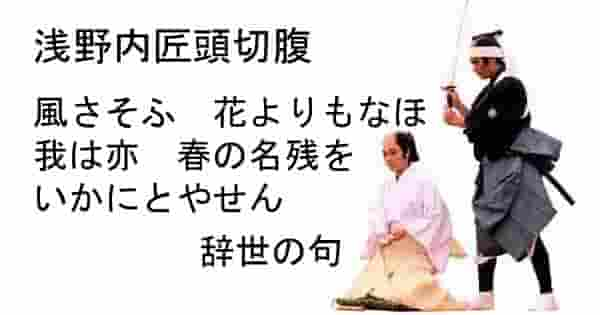赤穂事件年表(元禄十四年一月~六月)
| 1月28日 朝賀使吉良上野介は京都所司代松平紀伊守と共に京都御所に参内して天盃を賜る |
| 2月04日 幕府は浅野内匠頭長矩に勅使饗応役、伊達左京亮村豊に院使饗応役を命じる |
| 2月27日 勅使の柳原前大納言、高野前中納言、院使の清閑寺前大納言が京都を発つ |
| 2月29日 吉良上野介は江戸に帰り、将軍綱吉に復命の為、登城する |
| 3月10日 ■浅野内匠頭は竜ノ口の伝奏屋敷に入り勅使接伴の準備に入る ■勅使と院使が江戸に到着する |
3月11日 浅野内匠頭 持病発症■勅使の柳原前大納言、高野前中納言と院使の清閑寺前大納言が伝奏屋敷に到着する■浅野内匠頭はこの頃より持病に悩み服薬する |
3月14日 浅野内匠頭 切腹
■幕府は浅野内匠頭を田村右京太夫邸に預け即日の切腹を命じる ■第一使者の早水藤左衛門、菅野三平は午後五時頃に赤穂へ発つ ■第二使者の原惣右衛門、大石瀬左衛門は午後九時過ぎに赤穂へ発つ |
3月15日 浅野大学閉門■幕府は赤穂城の受城使に脇坂淡路守安照と木下肥後守公定を任命する■幕府は受城目付に荒木十左衛門政羽と日下部三十郎を任命する ■幕府は赤穂代官に石原新左衛門と門田庄太夫を任命する ■幕府は浅野大学に閉門を命じる |
| 3月17日 幕府は浅野家の江戸鉄砲州上屋敷と赤坂南部阪下屋敷を公収する |
3月19日 赤穂藩士総登城■幕府は浅野内匠頭を取り押さえた梶川与惣兵衛に五百石を加増する■赤穂へ第一及び第二の使者が到着し、大石内蔵助は総登城を命じて刃傷事件を告げる |
| 3月20日 大石内蔵助の指揮のもと、町民に対し六分替をもって藩札の交換を開始する |
| 3月26日 吉良上野介が高家筆頭を辞職する |
| 3月27日 大石内蔵助は藩士を城中に集めて大評定を行った結果、3月29日に無条件開城を決める |
| 4月05日 大石内蔵助は藩庫を開き士卒へ金子や米穀の分配作業を開始する |
| 4月12日 浅野藩士ら赤穂より退散を始める。大野九郎兵衛父子が夜中に逃亡する |
4月15日 無念 大石内蔵助■大石内蔵助は会所を城外の遠林寺に移し藩政の残務整理と開城の準備をする■浅野家永代祭祀の為、赤穂の寺院に田地、永代供養料を寄進する ■大石内蔵助は居を尾崎村おせどに移す |
4月18日 大軍集結■収城の両目付、両代官は城内を大石内蔵助の案内で検分する■大石内蔵助は三度にわたり主家の再興と吉良上野介義央の処分を懇願する ■受城使の脇坂淡路守が竜野から午後九時頃に四千五百四十五の軍勢と共に大手門に到着 |
4月19日 無血開城■受城使の木下肥後守が有年から午前三時頃に千五百の軍勢と共に塩屋門に到着する■大石内蔵助は赤穂城を受城使に引き渡す |
| 5月05日 大石内蔵助は遠林寺祐海に浅野長重(華獄院)、長直(久岳院)、長友(景永院)、長矩(冷光院)四公の日牌料を持って高野山へ行かせ奥の院に長矩の建墓をなす |
| 5月20日 大石内蔵助は遠林寺の祐海を江戸に派遣し、鏡照院を介して主家再興の運動をさせる |
| 5月21日 赤穂浅野藩政の残務整理をすべて終了する |
6月24日 浅野内匠頭百箇日法要■江戸では堀部安兵衛、奥田孫太夫、高田郡兵衛らが泉岳寺に参詣する■赤穂では花岳寺での法要に大石内蔵助始め、赤穂残留の諸士が参詣する |
| 6月25日
■大石内蔵助は海路、大坂を経て京都の山科に向かい六月二十八日に到着する。 ■画像は赤穂御崎の大石内蔵助銅像 |
元禄赤穂事件関連ページ
事件の年譜刃傷事件~赤穂開城 山科隠棲 吉良探索~討ち入り 泉岳寺~切腹~遺族事件の詳細刃傷事件~藩主切腹 浅野家断絶 吉良邸討入り 引き揚げ~泉岳寺 切腹~遺子の処罰
赤穂城・浅野家・吉良家赤穂城古写真など 浅野内匠頭長矩 吉良上野介・左兵衛
赤穂四十七士と萱野三平
表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮
不参加萱野重實
刃傷事件から赤穂城開城迄の年譜の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48