池田久右衛門(大石内蔵助の偽名)
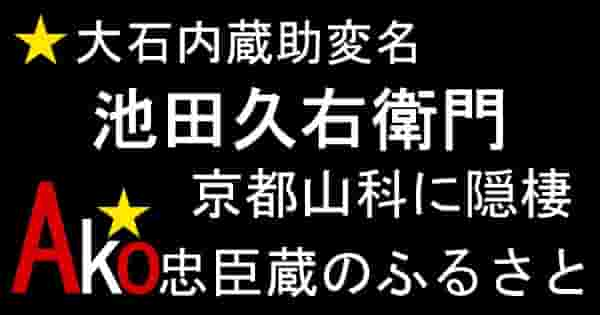
大石内蔵助は3部構成
赤穂城三の丸屋敷 広さは1900坪
大石邸長屋門
広さ千九百坪余りで本邸は享保十四年(1729)に焼失。長屋門と庭園が残っています。
浅野家断絶後、永井家の家臣篠崎長兵衛の屋敷の後、森藩の藩札の紙漉場になりました。明治になり家老藤井又左柄門の屋敷跡を中心に大石神社が創建され現在に至っています。
老僕八助
浅野家改易後の大石内蔵助
尾崎にある「おせど」は家扶瀬尾孫左衛門の兄元屋八十右衛門の別宅で、残務整理のために山科に発つまで内蔵助が家族と共に仮住まいをした場所、「大石内蔵助仮寓の地」として保存されています。画は赤穂を去るに際し、同村の老僕八助に与えたと伝わる内蔵助自筆の拓本ですが、画風に異論も出て真贋のほどは不明です。
赤穂を去る
大石内蔵助名残の松
御崎下の新浜港(現:伊和都比売神社)から大坂へ向かい元禄十四年(1701)六月二十五日に大坂に着いています。内蔵助名残の松は昭和二年に松食い虫により枯れ現在は二代目。初代の切り株が花岳寺に保存されています。京都山科に隠棲 池田久右衛門の誕生
赤穂藩の重臣進藤源四郎(四百石)の縁地で山科西野山村に源四郎を元受人として千八百坪の土地を購入し一年四ヶ月滞在する。現在地は京都市東山区山科西野山桜ノ馬場町。三月二十一日には山科近辺の土地を探して欲しい旨大石家の一族である石清水八幡宮の大西坊、専成坊、正之坊の三人に宛て、手紙を書いていて大石内蔵助のあだ名「昼行灯」とは真逆の迅速な対応に内蔵助の真の姿をみることができる。昭憲皇太后が詠む御詩に(明治十二年七月)大石内蔵助と題して「梅の花雪に埋もれて人知れず春をや待ちし山科の里」がある。山科を選んだ理由
- 京都東山と逢坂山との谷間の南へ広がる盆地で、東海道に近く京都や伏見にも近くて地理的条件が良かった。
- 石清水八幡宮は祖父大石義勝以来の縁地でそこの大西坊には内蔵助の弟、専貞が常住しその後内蔵助の養子覺連(叔父小山源右衛門の子)も入っていたこと。
- 江州石山の東の大石村には大石家の縁者も多く、特に浅野家の家臣進藤源四郎(物頭役四百石)が山科西野山村に先祖から田畑を所有していたので頼り、源四郎の身許保証を得て田地を買い入れ母方の姓である池田久右衛門と名乗って住居を構えた。
- 幕府の取り締まりが厳しく浪人が住居を構えるには庄屋、年寄、村役人の許可が必要だった。
遊興姿の内蔵助
山科での乱行 真意は?今でも謎
吉良の親族である伏見奉行の建部政字が大石内蔵助の動静を看視していたこともあり「ずぶ六と見せて心は酔いもせず」が内蔵助の本音であったのでは?と思いたいところです。山科での乱行が江戸急進派の堀部安兵衛や奥田孫太夫らとの間に意見の違いがあり、義盟が分裂寸前の状態の時期と符合するのは単なる偶然なのか。
伏見橦木町に通う人を「白魚大臣」といった。遊び代が九匁程度に対し京都から橦木町の駕籠代が五匁二分で駕籠代と遊び代が同程度だったことから竹代の高い白魚にちなむ。ちなみに、当時の祇園の遊女代金は三十匁程度だった。
お軽の話 本当だった!
[おかぢ] [おかや] [可留]だったとも云われる。生家は二文字屋で京都二条寺町で出版業とも古道具屋をしていたとも伝えられる。又、京都島原中ノ町の娼家の女だったとの説もある。十八歳で四十四歳の内蔵助のところに小間使い兼側女として入ったのは諸書が一致している。
子を宿すが子供のその後は不明。内蔵助は大西坊住職に宛てた手紙で、寺井玄渓や養子の大西坊覺連に生まれる子の将来を頼んでいる。
[お軽の墓]
京都上善寺に墓があり「清譽貞林法尼」が戒名。京都柴野瑞光院の過去帳には「清譽貞林法尼」正午三癸巳十月六日二十九往生二条京都坊二文字屋可留久右衛門妾也」とある。(註)正午三癸巳は正徳三年(1713)にあたります。
独り言大石内蔵助にはもう一人、お妾さんがいた。相生(おお)村在住(現相生市)で名は「お栄」。お栄さんには娘がいて名を「可音」と言った。元禄十四年二月十七日に四歳で亡くなっている。戒名は「玉室梅容」、墓は花岳寺の大石家墓域にあると教わった。「小山系譜」にも同様の記述があり、花岳寺に葬ったことが書かれている。
大石内蔵助の詩21首 雅号:可笑(かしょう)
- [今は早霞が関を立出て君ます里の花をいざ見ん]
- [とふ人に語る言葉のなかりせば身は武蔵野の露と答へん] 東へ下りて(義人遺草)
- [あらたのし思ひは晴るる身は捨つるうきよの月にかかる雲なし] 泉岳寺で(江赤見聞記・義人録)
- [よしの山よしやといゝもはてぬまに尚なけかるる世にもあるかな](菜華圓書翰)
- [何怨殺我身 一朝乍作塵 唯歓達君志 長不失為臣] 瑞光院主が江戸にて貰い帰りし辞世
- [桂花一朝雖開眉 思郷断腸不待夕](赤城義臣伝)註:桂花は木犀の花
- [存命て浮世の春は近けれど御法の花を待つぞ久しき](鐘秀記)
- [思ひ入る身は武蔵野の夕露の残る心は朝野下艸」(赤城義臣伝)
- [千代経ても老ひぬ例を常磐山色添ふ松に今ぞ知らるる]
- [濁江のにごりに魚のひそむともなどかはせみの捕らで止むべき]
- [水に映る花や藻屑に浮かべて散しを恨む岸の梅が枝]
- [木のもとに消すは有共吹風に散らば憂からん花のしら雲]
- [大井川今も御幸の址とめて秋は綿のとばり掛くらん] 寄松祝い
- [山の端を月の夕に打見れば松ばかりこそ峯に立ちけれ]
- [兎に角に思は晴るる身の上に暫し迷の雲とてもなし]
- [武士の命に高き名をかへて唯もかくこそあるまほしけれ]
- [池水にしばしが程は降り消えて凍る方より積る白雪]
- [しけかりし世のことわざを行かへてなみだひまなき年の暮れかな]
- [なかたなやさすがおかしき年の暮」(菜華圓書翰)
- [やぶれたる障子つづくるけさの雪](菜華圓書翰)
- [永らへて花を待つべき身なれどなほ惜しまるる年の暮かな]
大石内蔵助と大石りく
大石内蔵助その1大石内蔵助大石内蔵助その3大石りく(妻)
赤穂四十七士と萱野三平
表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮
不参加萱野重實
池田久右衛門の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48
