赤穂事件の要約(発端から終末迄)
赤穂事件とは?
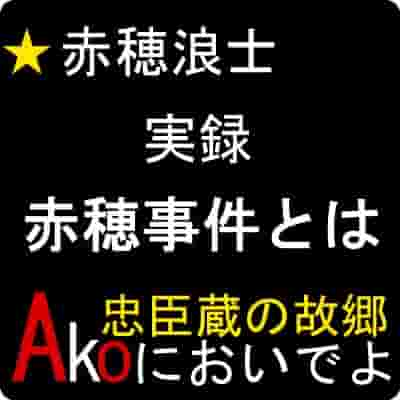
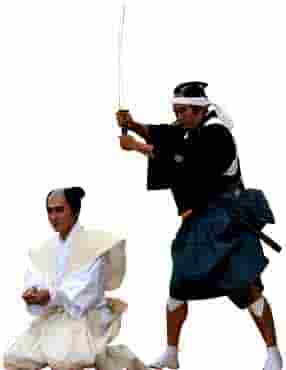
日本三大仇討ち事件
無念の切腹をした殿様浅野内匠頭の仇を討つために元赤穂藩士四十七人が起こした仇討ち事件で元禄赤穂事件とも呼ぶ。身分は家老から台所役人、足軽までさまざま。苦難に耐えて武士の面目に殉じた四十七士は今なお、日本人の心をゆさぶり続けます。浅野内匠頭の刃傷事件から吉良邸討ち入りを経て四十六士の切腹に至る経緯、ただ一人の生き残り寺坂吉右衛門のこと。仮名手本忠臣蔵の誕生と果たした役割も記しています。
ページ内ジャンプ 赤穂事件の発端吉良邸襲撃仮名手本忠臣蔵
独り言大石内蔵助しか知らなかった昔、連中は血に飢えた無頼の徒だと思っていました。諸書を読み少し理解が進むとその印象は真逆へと変わり、義理人情に厚く書を短歌を俳諧を漢詩、漢文を能くする知力の高い人々の集団だと分かったことでした。だからこそ命をかけた目標に向かい身分や信条や価値観の垣根を越えて結束することができたのだと確信するようになりました。
事件の発端から終焉迄の経過





発端は藩主の刃傷事件
勅使接待役を命じられた赤穂藩浅野家三代藩主浅野内匠頭長矩が指南役の高家筆頭吉良上野介義央を「この間の遺恨覚えたるか」と叫び突然、背後から斬りつけ、驚いて振り向いた吉良上野介の額にさらに斬りつけたことを指し江戸城松の廊下刃傷事件と呼ばれています。幕府の不公平な裁きが起因
元禄十四年(1701)三月十四日は将軍綱吉が朝廷からの使者に勅答する大切な日。勅使接待役の浅野内匠頭がご法度の刃傷事件を江戸城内で起こした事に将軍綱吉は激怒、徳川家始祖以来の不文律を忘れます。その結果、浅野内匠頭には「即日の切腹」を、吉良上野介には応戦をしていないことを理由に「お構いなし」を短慮に即断しました。浅野内匠頭の切腹は五万石の大名の扱いではなく罪人の扱いで、酒や煙草も許されず、遺言を書くことも、切腹のときに自分の刀を使うことも許されませんでした。この不公平な裁きが日本三大仇討ち事件の一つ「赤穂事件」の端緒となりました。
赤穂浅野家の断絶と失業
大石内蔵助木像
大石内蔵助本領発揮
残務整理や引き継ぎ、藩札の交換、残り金の配分、徹底抗戦を唱える武闘派と穏健派をまとめるなど様々な困難に耐えて無血開城を果たします。大石内蔵助は吉良上野介の処罰(喧嘩両成敗)を訴えつつ、浅野家の再興を第一に据え、あらゆるツテを使い莫大な資金を使ってお家再興を画策しているなか、閉門中の浅野内匠頭の実弟浅野大學長廣が広島浅野本家に差し置きと決まったことでお家再興の望みを断たれます。
武士の一分は仇討ち
喧嘩両成敗の願いも叶わず、お家の再興もならない結果となり、このことが最後の手段、武士の面目をかけた吉良邸への討ち入りにつながっていきます。大石内蔵助の苦悩
全ての整理を終えた大石内蔵助は船で赤穂を発ち、京都の山科に隠棲し家族と共に一時期を過ごします。吉良上野介の処罰の嘆願や浅野家再興の運動はこの時期にも行われ、お家再興による再仕官の期待から義盟に加わっていた浪士が望みを絶たれて四散し、百二十名余いた同志が五十数名にまで激減したのもこの時期でした。血判の同志分裂の危機
堀部安兵衛や奥田孫太夫などの仇討ち急進派とお家再興を第一とする派が対立します。京都山科と江戸間の意思の疎通は人を派遣(十二日前後)するか、飛脚による手紙だけの時代を考えると大石内蔵助の心労はいかばかりか、橦木町での遊興の時期と重なるのは単なる偶然なのか。
大石内蔵助にとりこの時期は家族との別れ、遊郭での遊興、お軽との出合いと別れ、円山会議での討入りの決定などがあり、二度と帰ることのない江戸への出発がありました。各地で仮住まいしていた赤穂浪士達も仇討ちのためにそれぞれ江戸に向かいます。
大石主税討ち入り姿
吉良邸襲撃の決行日
江戸での極貧生活に耐え 偽名をつかい、さまざまな職業に姿を変え、借家住まいをしながら吉良邸の探索が行われました。討ち入り資金とした瑤泉院(浅野内匠頭夫人)の化粧料の六百九十両(7000万円弱)が底をつく直前に吉良邸で茶会が開かれることを聞き込み、複数の情報源から間違いない事を確認して十二月十四日の討ち入りが決まります。
討ち入り隊の編成
討ち入りは表門と裏門の二隊に別れて突入しますが、四十七人の年齢や親子兄弟、武術の練達度などを基準に絶妙に振り分けられています。また装束、武具、近所への対応、負傷した仲間の扱い、泉岳寺への道順や隊列、幕府への自訴など細かく決められていて見事です。表門隊大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定 以上二十三士
裏門隊赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮 以上二十四士
裏門隊赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮 以上二十四士
不参加
萱野三平重實 元禄十六年(1703)一月十四日(主君の月命日)に大石内蔵助に同志だと言わしめた内容の遺書を残して摂津(大阪府箕面市)の自宅で自害しました。神文誓紙の手前、父親に仇討ちの企てを話せず、事情を知らない父の再仕官の勧めとの板挟みになったのが動機でした。忠臣蔵のふるさと赤穂市の大石神社には四十七士と並び人神として祀られています。
悲願成就の四十七士
戦闘は午前四時から二時間あまりで吉良上野介の首を挙げて決着します。吉良方の死者は十七人とも十九人ともいわれ、負傷者は二十四名にものぼりますが赤穂浪士側に死者はなく負傷者が四名でただけでした。吉良上野介の首と証拠のお守り袋は上野介の白小袖に包んで泉岳寺に帯同し主君の墓前に供えますが、遺骸は吉良上野介の寝所に運んで布団に寝かせ、屋敷内のロウソクなどの火をすべて消して高輪泉岳寺に引き揚げるなど後始末も見事でした。
四十六士切腹と寺坂吉右衛門
幕府の大目付仙石伯耆守邸に出頭を命じられ、門前で武具を放棄して簡単な事情聴取のあと四大名家に分けて預け先大名が決まります。親や妻子を残し、極貧の生活に耐えて主君の仇を討った四十六人はここでとわの別れを迎えるのでした。浅野内匠頭の切腹は即日を短慮に決めた将軍綱吉でしたが、赤穂浪士に対する世論は賛美一辺倒、幕閣は忠義の士を生かしてやりたい、学者は有罪無罪両論があるなか、ついに綱吉は決断して二月四日の切腹が決まります。
切腹は四大名家とも申し合わせたように一人5、6分と信じられない手際で進み、遺骸を桶に入れてその日のうちに泉岳寺に送り主君の墓域に埋葬されました。
寺坂吉右衛門は大石内蔵助ら幹部のかねての申し合わせの通り、泉岳寺までの間に隊列を離れ、その年の年末には故郷の姫路に戻っています。残された遺子の処罰なども記していますのでご覧ください。
赤穂事件と歌舞伎

仮名手本忠臣蔵とは?
奇しくも四十六士切腹から四十七年後(寺坂吉右衛門没の翌年)の寛延元年(1748)に竹田出雲、三好松洛、並木千柳合作による「仮名手本忠臣蔵」なる浄瑠璃が大坂竹本座で初演され、歌舞伎も大坂嵐三五郎座で初演されて大当たりします。翌年には江戸の森田座でも歌舞伎で初演されて以後、その人気から歌舞伎界の「独参湯」(気付け薬)と称され、その上演回数は幕末までに100回を越えるまでになります。
初演当時には四十七士が忠臣であるとの評価が定着していたこともあって赤穂浪士による復讐事件を「忠臣蔵」と呼ぶようになります。
また、その人気ゆえに実録と虚構が交錯した事柄も多く、史実探求をより困難にしている側面もあるようです。尚、外題の仮名手本は当時寺子屋で使われた教科書を指したことから忠臣の鑑(教科書)を意味する説のほか諸説があるようです。
赤穂事件のあらすじの頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48